在宅/テレワーク/リモートワークが縮小中!オフィス回帰の背景とは
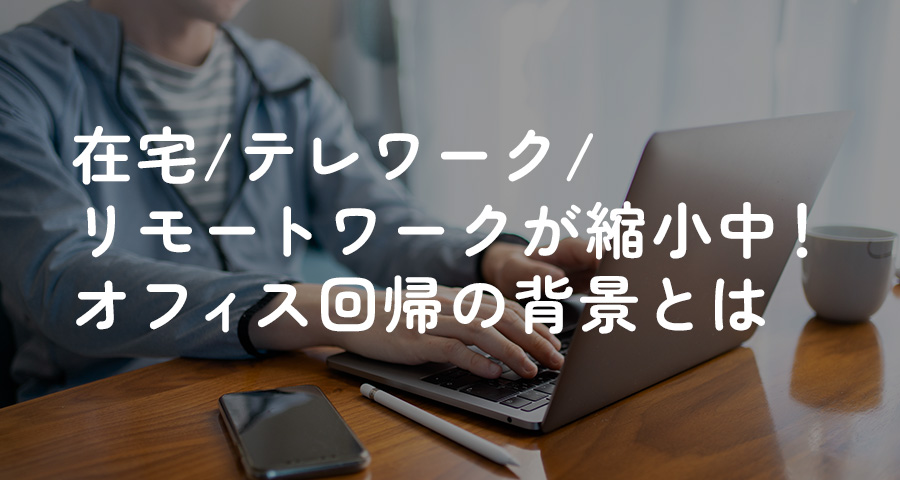
テレワークを廃止もしくは縮小してオフィス出勤を義務付ける「オフィス回帰」の動きが進んでいます。在宅/テレワーク/リモートワークが減少傾向となっている理由、どのような職種がオフィス回帰を進めているのか、さらにオフィス回帰といってもコロナ前と違う点などについて解説します。
目次
リモートワーク全盛からオフィス回帰の流れへ
令和5年度の国土交通省の発表によると、企業に雇用されている従業員の中で、テレワークを行っている人の割合は、全国で24.8%となりました。これは、最もテレワーク率が高かった令和3年の27.0%と比較すると2.2%減となっています。首都圏においては特に顕著で、令和3年に42.3%まで達していたテレワーク率は、令和5年時点で38.1%にまで減少しました。確実にオフィス回帰の流れは進んでいるといえます。
とはいえ、コロナ前のように完全出社に戻るとは限りません。テレワークを部分的に残しつつ、一定の日数出社を義務付けるハイブリッド型の方が主流です。週5~7日テレワークを認める会社は令和4年の18.7%から令和5年の17.7%まで減少しているものの、週1日から週4日までのテレワークを認める会社は令和4年の53.7%から令和5年の58.1%まで増加しました。
オフィスにもテレワークにもそれぞれの良いところがあり、双方を取り入れて多様な働き方を実現するという傾向が見えています。
参考:国土交通省「テレワーカーの割合は減少、出社と組み合わせるハイブリットワークが拡大~令和5年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~」
なぜオフィス回帰の流れがあるのか
働き方改革や多様な働き方という文脈からは逆行するように見えるオフィス回帰ですが、どのような理由があるのでしょうか。
オフィスの方がメンバーの業務管理をしやすい
テレワークの課題としてよく挙げられるのが「管理者としてメンバーの業務管理が難しい」という点。テレワークだとメンバーが業務に臨む姿を目で確認できないため、
・テレワーク中にしっかり業務にあたっているかわからない
・進捗が分かりづらい
・様子がわからないため業務上のトラブルやモチベーションの低下などのインシデントの発見が遅れる
などのリスクを感じる管理職は多いようです。オフィスで対面で業務にあたった方がメンバーの業務管理がしやすいと考え、オフィス回帰を進める企業が一定数います。
帰属意識の強化
フルリモートになり同僚や組織との対面での接触回数が減ることで、ただ決められた業務をこなしているだけという状態になりがちです。結果として、雇用されている会社に対しての帰属意識が減る傾向にあります。帰属意識が減ると
・業務へのモチベーションが下がる
・主体性が減る
・会社の事業や理念への理解度が低下する
・退職リスクが上がる
といったリスクが生じます。リアルな接触があった方が帰属意識は高まりやすいという認識を持っている企業は多いです。
対面で円滑なコミュニケーションをとりたい
テレワークでもZoomやTeams等でのオンラインミーティング、SlackやChatworkなどのチャットツールを使えば不足ないコミュニケーションを取れるという考えはありますが、対面より円滑さに欠けると感じる人は多いようです。
・対面よりもちょっとした質問やカジュアルな雑談がしづらい
・打ち合わせとなると、いちいち時間をセッティングして臨まないといけない(すぐにできない)
・チャットの場合、文面を吟味して投稿する必要があり、結果迅速なコミュニケーションでなくなることがある
こうしたことから、疑問を抱えたまま業務に臨むことになったり、同僚とのコミュニケーションが停滞することで孤独を感じる社員がいたりと、さまざまな面で支障をきたすケースが出てきます。
イノベーションの創出
また、アイデア出しやブレスト、雑談の中からの思いつきといったイノベーションの創出もテレワークだと発生しにくいと捉えている企業は多いようです。オンラインミーティングだと参加者と会話はできますが、どうしても情報交換や状況確認といった雰囲気になりやすく、その場での自由な議論はオンラインミーティングの仕組み上難しい面があります。
オフィスに戻る傾向の強い職種/業務
オフィスに戻る傾向が強い職種の代表例を挙げてみました。コミュニケーションやイノベーションという側面に重要度を感じている職種は、毎日ではなくてもオフィスで対面する日を設けることが増えています。
営業
営業は上司による業務管理が課題になりやすい職種です。SaaS等を活用して外出先や自宅でも業務の報告や事務書類の作成は問題なくできるようになりましたが、実際にどのような動きをしているかは見えづらく、さらに最近では個人プレーよりもチームで成果を出すという方向性の会社が増えています。そのため、オフィスへの出勤は復活しつつあります。
エンジニア
エンジニアはPCで業務を行う関係上、オフィスでなくても問題ない職種と思われがちですが、テレワークだと工数や稼働時間の管理が難しいケースがあります。また開発においては、コミュニケーションをとりやすい方が、ミスが少なくなり進捗が良くなるという考え方も。そのため、自社やクライアントのオフィスへの出勤が義務付けられるケースが増えています。
制作系の職種
デザイナーやWeb制作、動画制作など、制作系の職種もオフィス回帰が一定進みつつあります。アイデア出しやブレストなどのイノベーション面で、自宅で一人で業務を行うのは限界があるのと、社内の他部署からの情報などを吸収しやすい環境であることが良い制作物につながるケースがあるからです。
事務職
上記のような職種がオフィスに出勤を増やすことで、社内手続きや物品に関すること、人事労務に関する相談なども増え、総務や人事、管理部などの事務職も出勤する必要が増します。
在宅/テレワーク/リモートワークのままの傾向が強い職種
ITのマーケやコンサル系の職種はリモートワークのままが多い傾向がありますが、それでもフルリモートでなく出社をする日を設ける会社も見かけます。また、作業系の職種はフルリモートのままのケースが多いです。
IT無形商材を扱う職種
オンラインセミナーや情報商材を扱うコンサルタントは全てがオンライン上で完結する業務であることが多いため、社内がリモートワークにそもそも最適化されており、出勤する文化自体がないことがあります。
マーケティング
オンライン上での集客やSNS運用などを行うマーケティング職種もリモートワークが主流です。ただし、こちらはアイデア出しや報告などは必要な職種なので、週1から2日程度は出勤するようなケースもよく見かけます。
電話オペレーター、データ入力など
電話オペレーターやデータ入力などの作業系の職種はリモートワークのままになっているケースをよく見かけます。行う業務が定型であり、作業に使う道具やツールを在宅でも支給できるのであれば、オフィスに出勤して場所を取るよりはリモートの方が効率的との考え方があります。
オフィス回帰後に考慮すべき点とは
オフィス回帰がさまざまな企業で進む一方、コロナ前とは違う点もあります。
・週数回のテレワークは継続して許可しているケースが多い
・固定席ではなくフリーアドレス制の導入が増えている
このため、問題になるのは内線や代表電話への電話対応業務です。フリーアドレスだと、どこに誰が座っているかが日によって違うため内線表は無意味になります。さらに、常に全員が出社しているわけでなければ固定電話を各席に置くのもコストの無駄です。そのため、電話を全てスマホに切り替えるケースが増えています。
スマホであればオフィスでも在宅でも内線/外線両方の電話を取れます。オフィスにたまたま出勤している人に電話対応業務が偏ることもありません。
スマホ内線化をすればどこでも電話対応業務ができる
代表の固定電話番号にかかってきた着信を、メンバーのスマホでも取ることができるのが「スマホ内線化」です。さらに他メンバーへの取次もスマホ間ででき、まさに内線のような使い方も可能。スマホからの発信でも相手には固定電話の番号を表示できる等のメリットがあります。この機能があれば電話対応のためにオフィスに出勤する必要はなくなり、出勤するにしても本当に必要な業務にリソースをさくことができるはずです。
ソフトプラン株式会社の提供する「スマホ内線化サービス」は以下からご覧ください。

